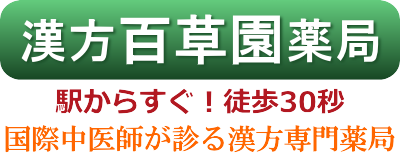ガンの定説

現在、ガンに対する一般的な定説は、ガン細胞は正常な細胞に由来し、ガン細胞になると周りの正常な細胞との共存を無視して増え続けると考えられています。
そして、増え続けるガン細胞は、最初にできた場所だけでなく、血液やリンパに乗って身体の他の場所にも移動し転移していき、さらにガン細胞は決してもとの正常な細胞にもどることがないという考え方です。

このような定説に基づいて、現在の一般的なガンの検査や治療は行われています。
具体的には、病理検査で顕微鏡によってガン細胞が発見されれば、ガン細胞は健康な人には無いわけですから、このままではがん細胞は増え続け死に至る危険もあるとされ、ただちにガン細胞を取り除く治療を開始しましょうとなるわけです。
このような考え方が推奨される早期手術の根拠となっており、疑問をもつ人はある時期まで誰もいませんでした。
定説への疑問
しかし、1982年に行われた日本ガン治療学会での「ヒトのガンの自然史」と題する特別講演で、ガンに対する定説に疑問が投げかけられました。
投げかけたのは、当時のガン研究所所長で細胞病理学の権威者である菅野春夫氏で、臨床的にガンの所見が全く無くて死亡した高齢者の遺体を解剖したデータの解析でした。
その内容は、
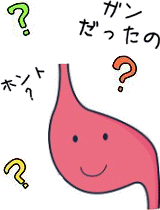
というものでした。
臨床的にガンの所見が全く無くて死亡した人でも、死後の解剖で詳しく検査するとほとんどの人にガン細胞があったとする細胞病理学権威者によるこの発表は、これまでのガンに対する定説を根底から揺るがせるものでした。
定説の「ガン細胞は全て無制限に増え転移する」という考えは実は正しくはなく、体内にガン細胞があっても無制限に増えることなく、健康を脅かすこともなく長年そのまま普通の健康な生活を送ることもできるということです。
もちろん、全てのガン細胞がこのようおとなしいガン細胞ではなく、無制限に増えて転移を起こし死にまで追い込む「悪性のガン細胞」もあります。
「おとなしいガン細胞」と「悪性のガン細胞」
病理検査で顕微鏡によってガン細胞が見つかっても、そのガン細胞が「おとなしいガン細胞」であることも多いのですが、残念ながら現在の技術では「おとなしいガン細胞」なのか「悪性のガン細胞」なのかを見分けることはできません。

このような「おとなしいガン細胞」と「悪性のガン細胞」が存在するのは、ガン細胞の増殖に係る「ガン免疫」の働きに強弱があるためだといわれています。
したがって、ガン細胞が発見されたならば、「ガン免疫」の働きを調べて強化することがガン治療には重要なポイントで、特に再発防止予防には非常に大切です。